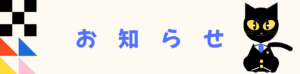【コラム】「著作物」に該当するものってどんなもの??著作権法上の定義や種類について【行政書士が解説】
-1008x1024.png)
※本コラムは、令和7年8月8日時点の情報をもとに作成されております。
著作権というと、クリエイターやアーティストなどの芸術活動を行う方が想像されやすいかと思われますが、インターネットで気軽にブログや画像、動画などを発信できるようになった現代社会においては、誰しもが著作権の保護の対象となり得ます。
その反面、知らず知らずのうちに、誰かの著作権を侵害してしまうという危険性も、以前に比べて増してきているように思えます。
著作権法(昭和45年法律第48号)の規定により、「著作物」を創作した著作者は、著作物を「複製」する権利や、著作物を「公衆送信」する権利など、その著作物の利用に関する複数の権利を専有するため、一定の場合を除き、他の人が著作者の許可を得ずにその著作者の著作物を利用してはいけません。
それでは、そもそもここでいう「著作物」とはいったいどのようなものを指すのでしょうか?
今回は、著作権の対象となる「著作物」の定義や種類について解説いたします。
目次
「著作物」とは
著作物の定義
まずは、法律上どのようなものが、「著作物」に該当するのか、その定義を見てみましょう。
著作権法第2条第1項第1号では、著作物を次のとおり定義しています。
著作権法(条、号等の漢数字は、算用数字、括弧でくくった数字に修正しています。以下同じです。) ※令和7年8月8日時点の条文です。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
(以下略)
つまり、著作物として認められるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。

上記のとおり、著作物は「表現したもの」ですので、例えば、アイディアは著作権では保護されません。アイディアに基づいて、それを具体的に表現したもの(論文や図面など)が著作物となります。
アイディアを保護する権利としては、特許権や実用新案権などがあります。
著作物の種類
一般的な著作物の例示
著作権法では、上記のように著作物を定義することに加えて、第10条第1項で、次のとおり著作物を例示しています。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(著作物の例示)
第10条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。
⑴ 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物
⑵ 音楽の著作物
⑶ 舞踊又は無言劇の著作物
⑷ 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物
⑸ 建築の著作物
⑹ 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
⑺ 映画の著作物
⑻ 写真の著作物
⑼ プログラムの著作物

注意していただきたいのが、こちらの規定は、飽くまで著作物を例示したにすぎないということです。
ここに例示されていないものであっても、前述の著作権法第2条第1項の定義に該当するものであれば、著作物として保護される可能性があります。
二次的著作物
上記の例のほかにも、「二次的著作物」という著作物もあります。
二次的著作物は、著作権法第2条第1項第11号で次のとおり定義されています。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴-⑽の3 (略)
⑾ 二次的著作物 著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案することにより創作した著作物をいう。
(以下略)
簡単にいうと、既存の著作物に新しい創作行為を加えて作成した著作物が、「二次的著作物」となります。
具体例を挙げると、
などがあります。

二次的著作物の基となった著作物の著作者、つまり「原作者」は、その二次的著作物の利用に関し、その二次的著作物の著作者が有する著作権と同一の種類の権利を専有します。
編集著作物
「編集著作物」というものも著作権法で定められています。
編集著作物を規定した著作権法第12条の規定は、次のとおりです。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(編集著作物)
第12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項の編集物の部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
具体例を挙げると、
などがあります。
なお、その編集著作物に該当するか否かは、構成する「素材」が著作物であるかどうかにはかかわりません。例えば、英語単語集なんかも、素材の選択や配列の仕方に創作性があれば、編集著作物になります。
素材の選択や配列の創作性に着目して、それを構成する個々の素材とは別に、編集物自体が独立して保護されます。

著作権法第12条第1項に規定のとおり、編集著作物として扱われるためには、素材の選択や配列に創作性があることが必要ですのでご留意ください。
データベースの著作物
編集著作物の規定の中では、「データベース」が除かれていましたが、別に「データベースの著作物」というものも、著作権法に定められています。
データベースの著作物を規定した著作権法第12条の2の規定は、次のとおりです。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(データベースの著作物)
第12条の2 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
2 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。
データベースの著作物に該当するか否かも、構成する「情報」が著作物であるかどうかにはかかわりません。

著作権法第12条の2第1項に規定のとおり、データベースの著作物として扱われるためには、情報の選択や体系的な構成に創作性があることが必要ですのでご留意ください。
なお、「データベース」については、著作権法第2条第1項第10号の3で次のとおり定義されています。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴-⑽の2 (略)
⑽の3 データベース 論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
(以下略)

電子計算機というのは、「コンピュータ」のことです。
コンピュータで検索できるか否かで「編集著作物」か「データベースの著作物」か区別されます。
具体例を挙げると、
などがあります。
共同著作物
二人以上が共同して創作した物を対象とした「共同著作物」というものも、著作権法に定められています。
共同著作物を規定した著作権法第12条の2の規定は、次のとおりです。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑴-⑾ (略)
⑿ 共同著作物 2人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。
(以下略)
具体例を挙げると、
などがあります。
この共同著作物ですが、条文を見ると該当要件は、次の二つがあります。
例えば、それぞれ別の人間が作成した小説と挿絵のように、分離して利用することが可能であり、それぞれが個別に著作物となるようなものは、要件に当てはまらないため、共同著作物に該当しません。

その他にも、歌詞と楽曲でできた音楽の著作物なんかも分離して利用することができるので、共同著作物に該当しません。
これらの著作物を「結合著作物」ということがありますが、著作権法上ではなく、講学上の概念です。
保護を受ける著作物と受けない著作物
著作権法の保護を受ける著作物
ここまで著作物の種類について解説してきましたが、上記の著作物に該当したとしても、その全てが著作権法による保護を受ける著作物とは限りません。
著作権法第6条では、さらに著作権法の保護の対象となる著作物を定めています。
その規定は、次のとおりです。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(保護を受ける著作物)
第6条 著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
⑴ 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
⑵ 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたものを含む。)
⑶ 前2号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
この第6条の各号のいずれかに該当しないと、たとえ著作物となる要件を満たしていても、日本の著作権法の保護を受けることができません。

第6条の柱書を見ると「この法律による保護」と書かれています。
つまり、この三つの条件に該当しなくても、外国の著作権法で保護を受ける可能性はあります。
日本国民の著作物
それぞれの条件についてみてみましょう。まずは、第1号の「日本国民の著作物」であるという条件です。
括弧書きで記されておりますが、ここでいう「日本国民」には、「日本の法令に基づいて設立された法人」と「国内に主たる事務所を置く法人」を含みます。

日本国民が創作した著作物であれば、国外で発行されたものも対象となります。
最初に国内において発行された著作物
第2号の条件は、「最初に国内において発行された著作物」であるというものです。
こちらも括弧書きで対象を広げているのですが、「最初に国外において発行されたが、その発行の日から30日以内に国内において発行されたもの」も含まれています。

外国人が創作した著作物であっても、「最初に国内で発行されたもの」や「最初に外国で発行されたが、その発行の日から30日以内に国内で発行されたもの」であれば、日本の著作権法の保護の対象となるということですね。
条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
第3号の条件は、「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」であるというものです。
ここでいう条約として、ベルヌ条約、万国著作権条約、TRIPS協定などがあります。これらの条約に加盟している国の国民の著作物やこれらの条約国で最初に発行された著作物が保護の対象となります。
保護を受けない著作物
著作権法では、著作物に該当するものであっても著作権の目的とならないものを定めています。
その規定は、次のとおりです。
著作権法 ※令和7年8月8日時点の条文です。
(権利の目的とならない著作物)
第13条 次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
⑴ 憲法その他の法令
⑵ 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
⑶ 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
⑷ 前3号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
法令や官公庁などが発する告示、訓令、通達など、裁判所の判決などが著作権の目的とならない著作物とされています。

第2号について、国や地方公共団体などの官公庁が発行する全ての文書が権利の対象外というわけではなく、白書のような報告書などは著作権の対象となりますのでご注意ください。
終わりに
いかがだったでしょうか?
今回は、「著作物」について著作権法上の定義や種類を解説させていただきました。
SNSを利用しているときや、仕事の資料を作っているときなど、日常の中でふとしたときに「あれ、そういえば、これって著作権的に大丈夫かな……?」と思う瞬間が誰にでもあるかと思います。
そんなときに、ぜひこのコラムの内容を思い出していただければ幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。

行政書士事務所 稲穂ONEでは、著作権登録申請サポートを行っています!
お手続についてお悩みの方は、お気軽にお問合せください!
| 〒047-0032 北海道小樽市稲穂1丁目12-1 マリンシティ101号室 行政書士事務所 稲穂ONE TEL:070-9146-6548 ご依頼・お問合せはこちら 行政書士 佐藤 千峰 |
投稿者プロフィール
-
職業:行政書士
経歴:平成30年4月から令和6年12月まで地方公務員として勤務。主に、住民税の賦課業務、例規および重要文書の審査業務などに従事。令和7年5月に行政書士事務所を開業
取扱業務:会社設立サポート、補助金申請サポート、著作権登録申請サポートなど
資格:行政書士、著作権相談員
最新の投稿
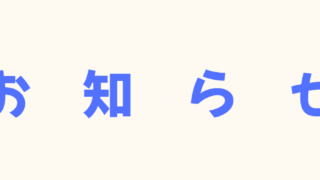 お知らせ2026年1月15日【お知らせ】「古物商許可申請サポート」を取扱業務に加えました。
お知らせ2026年1月15日【お知らせ】「古物商許可申請サポート」を取扱業務に加えました。 活動報告2025年12月28日稲穂ONE活動報告(2025年11月・12月)
活動報告2025年12月28日稲穂ONE活動報告(2025年11月・12月) 活動報告2025年11月30日稲穂ONE活動報告(2025年10月)
活動報告2025年11月30日稲穂ONE活動報告(2025年10月)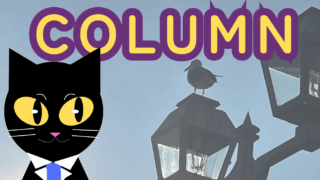 コラム2025年11月28日【コラム】「認定特定創業支援等事業」ってどんな制度??創業者が必ず受けるべき理由とは??
コラム2025年11月28日【コラム】「認定特定創業支援等事業」ってどんな制度??創業者が必ず受けるべき理由とは??